
公務員って有給はしっかりとれるのかな?1年でどれだけ取れるんだろう?
ワークライフバランスがしっかりしており、有給休暇も充実していると考え、公務員を志した人もいるかもしれません。
では、本当に公務員であれば、企業よりも有給休暇消化率は高いのでしょうか?
この記事では、公務員の有給休暇に関する基本的な知識や、消化率や有給以外の特別休暇などを徹底的に解説します。
公務員の有給休暇に興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
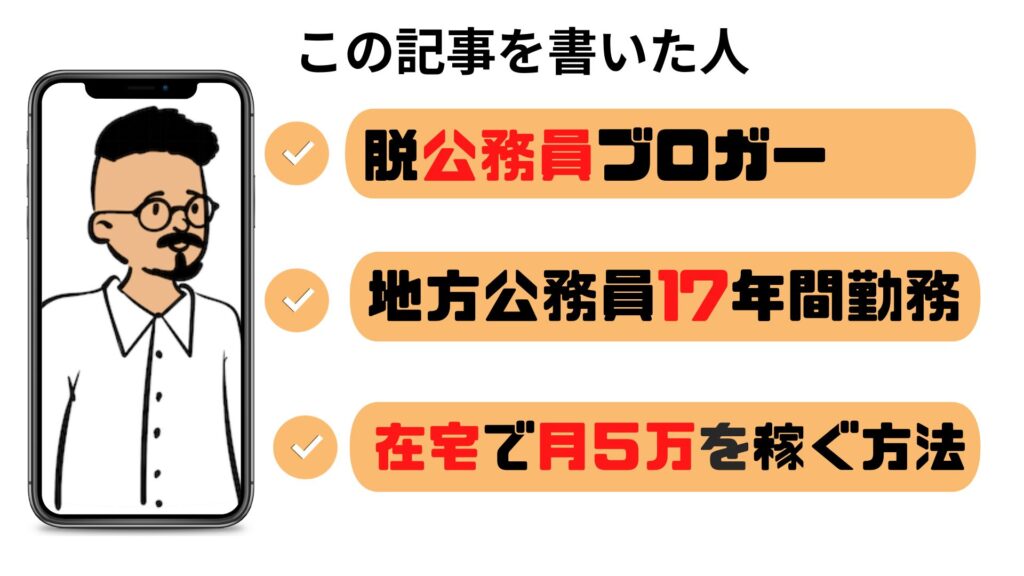
「公務員」は本当に「安定」しているの?
・給料安い【子供を大学進学させれる?】
・減り続ける退職金【老後は大丈夫?】
・転職スキルなし【公務員って価値ある?】
このまま、何もしなければ「不幸」な老後が待ってます。
自分で稼げるように「行動」が必要です。
>>公務員でもスグに3200円稼げるポイ活!
>>「今だけ」無料の投資講座を受ける
>>毎日コツコツ3000円稼ぐ方法
公務員の有給休暇の付与日数や繰り越し制度は?

公務員の有給休暇の付与日数はどれくらい?
公務員の有給休暇は、毎年1月1日に20日もらえます。
年度途中に入った人は、働き始めた月で有給の付与日数が変わります。
たとえば、4月から採用される1年目の職員は、15日もらえます。
民間企業は、労働基準法が適用されるので以下のように勤続年数が増えるとともに、付与日数も増えていく仕組みです。
| 勤続年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

公務員の方が有給休暇でも恵まれているんだね。
公務員の有給休暇の繰り越し制度はどうなっている?期限や上限は?
前年に使わなかった分は、翌年に持ち越せますが、20日が上限です。
すなわち、最大で40日まで貯められます。
40日より多くなると、余った分はなくなってしまいますので気をつけましょう。
公務員の有給休暇は1時間単位で取得できる
一般的に、民間企業では有給休暇を取得する際、半日や1日単位が一般的ですが、公務員の場合は「1時間単位」での取得が可能です。
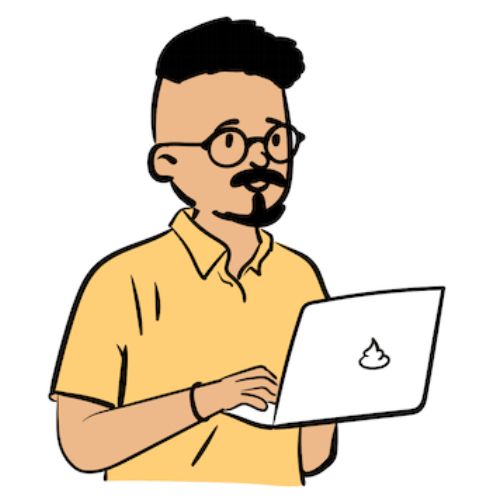
公務員時代、私は子どもの学校行事に参加するために、朝の1時間休むことが多くありました。
このように、時間休を使うことで、自分の都合に合わせて休暇を調整できるので、仕事とプライベートの両立がしやすくなります。
公務員の有給休暇の消化率はどれくらい?国や地方自治体、職種別のデータを分析

公務員の有給休暇の消化率の平均は?民間企業との比較や推移を分析
総務省が発表した統計資料をまとめると以下の通りです。
| 都道府県 | 政令指定都市 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|
| 取得日数(日) | 12.3 | 14.0 | 11.0 |
民間企業と国家公務員との有給消化日数を比べると、 民間企業は平均で10.1日で、 国家公務員は平均で14.9日でした。

公務員の方が年間で約5日間は消化率がいいんだね。
公務員は年に5日は有給休暇を取る義務がある?
公務員の有給休暇の取得推進について、まずはお伝えします。
公務員は、どんな役職でも、年に5日は有給休暇を取らなければなりません。これは、国家・地方公務員のルールです。
国家公務員の場合、人事院が2018年8月10日に、有給休暇の取得に関する具体的なルールを決めました。それは、以下のようなものです。
さらに、民間労働法制における年次有給休暇の時季指定に係る措置を踏まえ、年次休暇の使用を促進するため、各省各庁の長は、休暇の計画表の活用等により、一の年の年次休暇の日数が10日以上の職員が当該年において年次休暇を5日以上確実に使用することができるよう配慮することとする。
引用元:2018年8月10日 公務員人事管理に関する報告
1年に10日以上の有給休暇がもらえる職員は、年に5日は必ず使わないといけません。これは、国家公務員と地方公務員の共通のルールです。

公務員は年に5日は有給休暇を取る義務があると言いましたが、これは人事院の決めたルールです。民間企業に法律で決まっている労働基準法とは違います。法律で強制されているわけではないのです。
公務員の有給休暇以外の特別休暇を紹介

それでは、この章では有給休暇以外の休暇制度について解説していきますね。
公務員の特別休暇
公務員においても、国や自治体によって異なる法律や条例に基づいて特別休暇が規定されています。以下は一般的な特別休暇の事由です。
これらの特別休暇は、「給与の減額なしに休暇を取得できる」ということが特徴です。ただし、特別休暇は特定の事由がなければ取得できないという制約があります。
特別休暇には、自治体ごとに異なりますが、一般的な日数を挙げると、以下のようになります。
- 忌引休暇: 親族との関係により変動する
- 夏季休暇: 5日間
- ボランティア休暇: 5日間
- 結婚休暇: 5日間
- 育児に伴う授乳のための休暇: 一日2回30分以内
- 出産休暇: 産前8週、産後8週
- 妻の出産に伴う休暇: 2日間
- 子の看護休暇: 子一人につき、5日間
- 生理休暇: 必要な日数分
公務員の忌引休暇
公務員の忌引き休暇の日数は各自治体で異なってきますが、国家公務員の特別休暇に準じて定める自治体が多くなっています。
ここでは、国家公務員の忌引き休暇日数を紹介します。
| 関係 | 日数 |
|---|---|
| 配偶者 | 7日間or10日間 |
| 両親 | 7日間 |
| 義両親 | 3日間 |
| 子供 | 5日間 |
| 兄弟や祖父母 | 3日間 |
| 叔父・叔母 | 1日間 |
公務員の夏期休暇
公務員にはお盆休みがない代わりに、「夏期休暇」と呼ばれる夏休みが与えられます。この夏期休暇は、通常7月から9月の期間に5日間取ることができます。
柔軟性があり、5日分を連続して取得するか、1日ずつ分けて取得するか、自分の都合に合わせて選ぶことができます。
ただし、夏休みは時間休のように1時間単位での取得はできませんので、注意が必要です。この点を踏まえ、計画的に休暇を取得することが重要です。
ちなみに、夏休みは使い切らないと消滅してしまいます。有給休暇のように翌年に繰り越すことができないので注意してください。
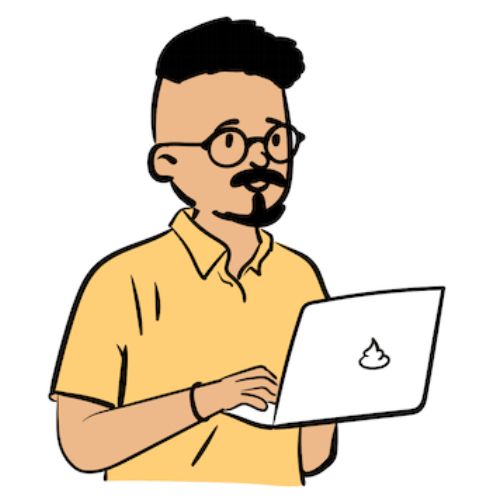
私の公務員時代はお盆の期間に取りたい人が多かったので、私は8月下旬から9月にかけて夏休みを取ることが多かったです。
公務員の年末年始休暇
公務員の年末年始の休暇は、12月29日から1月3日までの合計6日間となります。その前日である12月28日は仕事納めとなり、新年の1月4日が仕事初めです。
年末年始は業務を進める期間というよりも、挨拶周りの対応がメインとなります。この時期は、年始のご挨拶や新年のスケジュールの確認などが中心となり、業務自体は比較的静かな時期となります。
公務員の病気休暇と休職
以下の記事で詳しく解説しています。
公務員の育児休暇
以下の記事で詳しく解説しています。
子ども看護休暇【公務員ならではのサポート】
病気や急な体調不良に見舞われた際、子どもの看護をすることは親にとって当然の責務です。その中でも、公務員の特典である「子ども看護休暇」は、頼もしいサポートとなっています。
自治体によって変わりますが、私が働いていた自治体は5日間の子ども看護休暇が与えられていました。これは、兄弟姉妹がいる場合でも最大10日間までのサポートが受けられます。
まとめ
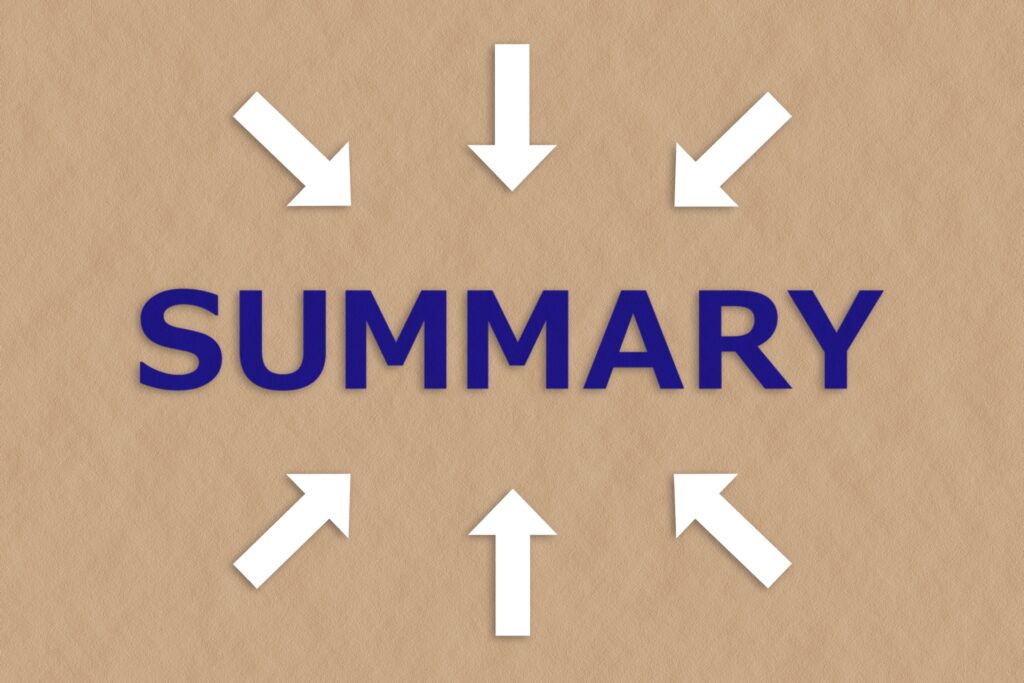
このブログでは消化率や取得方法などを徹底解説しました。
公務員の有給休暇は、一般の会社員と比べてもかなり優遇されていることが分かります。また、有給休暇の取得には計画性と交渉力が必要です。自分の仕事の進捗や周囲の状況を把握し、上司や同僚とコミュニケーションをとりながら、適切なタイミングで休暇を申請しましょう。
公務員の有給休暇は、自分の心身の健康やモチベーションを高めるための大切な権利です。ぜひ、積極的に活用してください。
「公務員」は本当に「安定」しているの?
・給料安い【子供を大学進学させれる?】
・減り続ける退職金【老後は大丈夫?】
・転職スキルなし【公務員って価値ある?】
このまま、何もしなければ「不幸」な老後が待ってます。
自分で稼げるように「行動」が必要です。
>>公務員でもスグに3200円稼げるポイ活!
>>「今だけ」無料の投資講座を受ける
>>毎日コツコツ3000円稼ぐ方法





