
公務員のボーナスはいつ、いくらもらえるの?計算方法わかれば教えてほしいな。
公務員だけでなく、働く皆さんにとって、年末や年度末に支給される賞与(ボーナス)は待ち遠しいですよね。
そのなかでも「いつ」「いくら」もらえるの?っていう疑問が多いですね。
今回はそれらの疑問も含めて、公務員のボーナスを徹底解説します。
>>【2023年最新】公務員のボーナスは?給料上がるのはいつから?
- 公務員のボーナス支給額計算方法
- 公務員のボーナスで注意すること【病気休暇・休職・転職】
- 公務員のボーナスは多すぎる【平均は?】
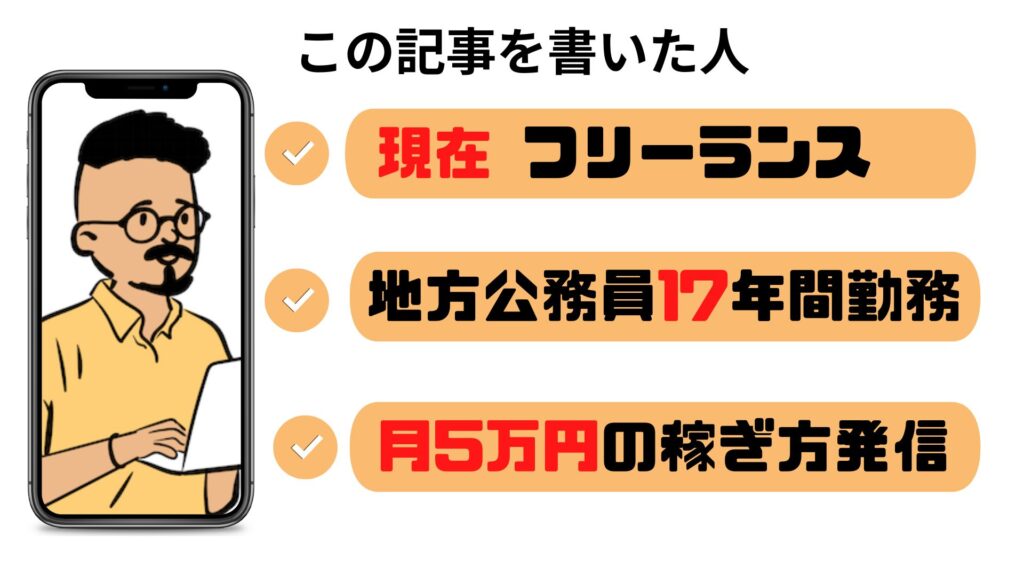
「公務員」は本当に「安定」していますか?
- 給料安い【子供を大学進学させれる?】
- 減り続ける退職金【老後は大丈夫?】
- 転職スキルなし【公務員ってスキルある?】
このまま、「副業禁止だから…」って、何もしなければ「不幸」な老後しか見えません。
早く動き出さないと、時代から取り残されてしまいます。
>>【2023年最新】公務員バレてもOK!副業7選【合法裏ワザ】
>>「今だけ」無料の投資講座を受ける
>>副業バレをビビっている公務員はコレがおすすめ!
公務員のボーナス金額はいつ?いくら?【支給額計算方法を解説】

公務員の皆さんにとって、ボーナスの金額が具体的にどのように決まるのか、公務員であるならば知っておいた方がいいです。
ここでは、公務員のボーナス金額がどのように決まるのかについて、詳しく解説していきます。
ボーナスの支給額は、組織や地域によって異なる場合がありますが、一般的な支給額計算の仕組みをご紹介します。
ボーナス支給額=
(基本給+扶養手当+地域手当)×支給月数

具体的な数字を出して教えてほしいな。
(30万円+2万円+1万円)×4.4(2022年実績)=約145万円
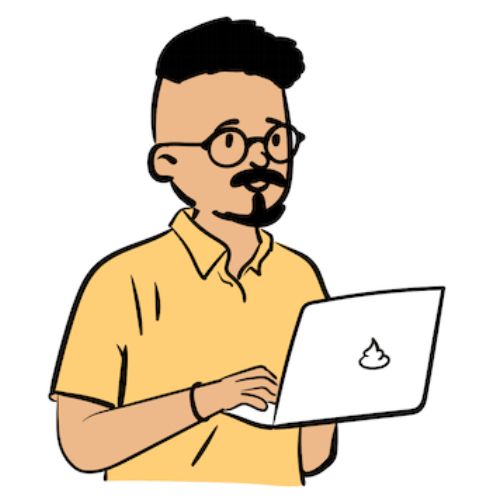
自分の基本給に置き換えてくださいね。
次からは、賞与(ボーナス)を構成する以下の言葉の意味を詳しく解説します。
- 基本給とは
- 扶養手当とは
- 地域手当とは
- ボーナス支給月数
- ボーナス支給日
基本給とは【公務員の給与体系の基盤】
公務員の給与体系は、基本給を基準にしてさまざまな手当や特別給与が加算・減算されることで構成されています。ボーナス支給額の計算も、基本給を基礎として行われています。
民間企業でいう基本給のことを、国家公務員では「俸給」、地方公務員では「給料」と呼びます。
国家公務員法と地方公務員法で基本給の呼び名を定めています。

同じ公務員なら同じ呼び方にしたらいいのにね..
公務員の基本給(俸給)は、毎年人事院が公表する「俸給表」に基づいて決定されます。
俸給表とは、わかりやすく言えば民間企業の「給与テーブル」に相当するものです。
人事院が、業種・職種・従業員の役職ごとに民間企業の給与支給額を調査して平均を算出し、公務員の給料テーブルである俸給表を作成しています。
扶養手当とは
公務員が配偶者や子供などを扶養している場合に支給されます。
支給額は、扶養家族の人数や年齢、配偶者の収入などに基づいて計算されます。一般的に、扶養家族が多いほど支給額が増える傾向があります。
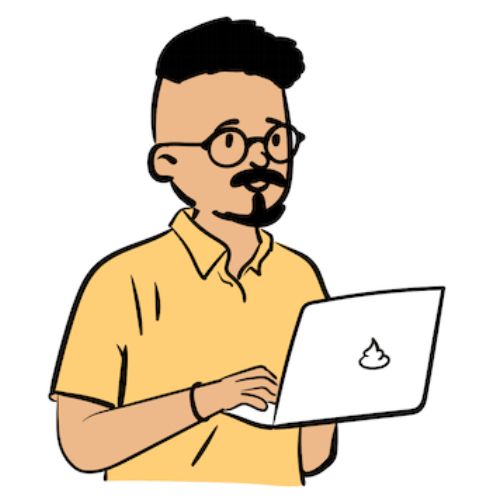
ちなみに私の働いていた自治体は配偶者は6,500円、子は10,000円でした。
地域手当とは【計算方法】
地域手当の支給額は、地域によって異なります。
一般的に、都市部や大都市圏などの経済的に活発な地域では支給額が高くなる傾向があります。
一方、地方部や人口の少ない地域では支給額が低くなる場合もあります。
地域手当の計算方法は、各地方自治体や組織によって異なることがありますが、一般的な方法としては以下のように計算されます。
地域手当=
(給料+管理職手当+扶養手当)×支給率
地域手当の支給率が高い地域は東京
地域手当は、都道府県の約7割、市町村の約2割で支給されています。
その中でも、東京都特別区で勤務している職員の支給率は20%と一番高額です。
大都市、特に東京のような地域では、生活費が高いという現実があります。
このような物価の差によって、地域間で生活水準の格差が生まれる可能性があります。この格差を調整するために地域手当が設けられています。
その他では、政令指定都市になっている人口が多い地域の支給割合が高いです。
ボーナス支給月数
人事院という機関が毎年8月に人事院勧告というものを行って、国家公務員のボーナス支給月数を決めます。
人事院は、「国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させる」ことを基本としています。これを「民間準拠」といいます。
同じ条件(役職段階、勤務地域、学歴、年齢階層)にある者同士の官民の給与を比較した上で、勧告をすることになっています。
地方公務員は人事院勧告を見てから自分たちの自治体のボーナス支給月数を決めていきます。
自治体の財政事情により変わりますが、ほとんどが国が決めた月数を用います。
公務員のボーナス支給日はいつ?
以下の表のとおり、国家公務員の夏のボーナス支給日は6月30日、冬のボーナス支給日は12月10日と定められています。 【人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当】
| 夏のボーナス | 6月30日 |
| 冬のボーナス | 12月10日 |
地方公務員は各自治体の条例によって自由に決めれますが、ほとんどが国家公務員に準じて支給されます。
公務員のボーナスで注意すること【病気休暇・休職・転職】

公務員のボーナスは嬉しいものですが、特定の状況下では支給に関して注意が必要です。
病気休暇や休職、転職など、公務員が直面する様々な状況によって、ボーナスの受け取りに影響が生じることがあります。
以下に該当する方は注意しなければいけないことがあります。
- 病気休暇中、休職中
- 育児休暇を取得している
- 退職、転職をしようと考えている
これらに該当している方はボーナスの基準日というものに注意しなけければなりません。
ボーナスの基準日は支給日とは別に設定されていて、夏のボーナスの基準日は6月1日、冬のボーナスの基準日は12月1日と設定されています。
| 基準日 | 支給日 | |
|---|---|---|
| 夏のボーナス | 6月1日 | 6月30日 |
| 冬のボーナス | 12月1日 | 12月10日 |
なぜ基準日に注意しなければいけないかというと、基準日を基準にボーナス支給の有無が変わってきます。
病気休暇・育児休暇を取得している方
基準日から数えて半年以上病気休暇、育休期間だと支給されません。
基準日より前の半年間の勤務状況でボーナスの支給は判定するので、判定するための期間が全て、病気休暇、育休期間だとボーナスは支給されません。
退職予定の方
退職するときは基準日が重要です。
その理由としては公務員のボーナスは基準日の1か月前以内が退職日の場合、支給日が退職後であってもボーナスが支給されるからです。
つまり、2023年夏のボーナスであれば、5月1日以降の退職であれば、辞めた後でもボーナスが支給されます。
損しないためにも、基準日を意識して退職、転職を考えましょう。
公務員のボーナスは多すぎる?【年齢別で算出】

公務員のボーナスは、一部からは高額であるとの意見もあります。
これまでの公務員のボーナスで用いられた具体的な支給月数の推移を見ていきましょう。
以下が、人事院が出している歴代のボーナス月数です。

国家公務員【総合職】のボーナス平均
具体的にいくらのボーナスが支給されるのでしょうか。発表されている公的な資料から探ってみましょう。
| 職種 | ボーナス |
|---|---|
| 国家総合職(30歳) | 約160万円 |
| 国家総合職(40歳) | 約190万円 |
| 国家総合職(50歳) | 約360万円 |
参考:令和4年国家公務員給与等実態調査報告書
国家公務員【一般職】のボーナス平均
| 職種 | ボーナス |
|---|---|
| 国家一般職(30歳) | 約110万円 |
| 国家一般職(40歳) | 約160万円 |
| 国家一般職(50歳) | 約180万円 |
参考:令和4年国家公務員給与等実態調査報告書
地方公務員【都道府県庁】のボーナス平均
| 職種 | ボーナス |
|---|---|
| 都道府県庁(30歳) | 約100万円 |
| 都道府県庁(40歳) | 約145万円 |
| 都道府県庁(50歳) | 約165万円 |
参考:令和4年国家公務員給与等実態調査報告書
地方公務員【市町村】のボーナス平均
| 職種 | ボーナス |
|---|---|
| 市町村(30歳) | 約97万円 |
| 市町村(40歳) | 約140万円 |
| 市町村(50歳) | 約160万円 |
参考:令和4年国家公務員給与等実態調査報告書
地方公務員は国家公務員と異なり、自治体によって支給額は変動します。
まとめ
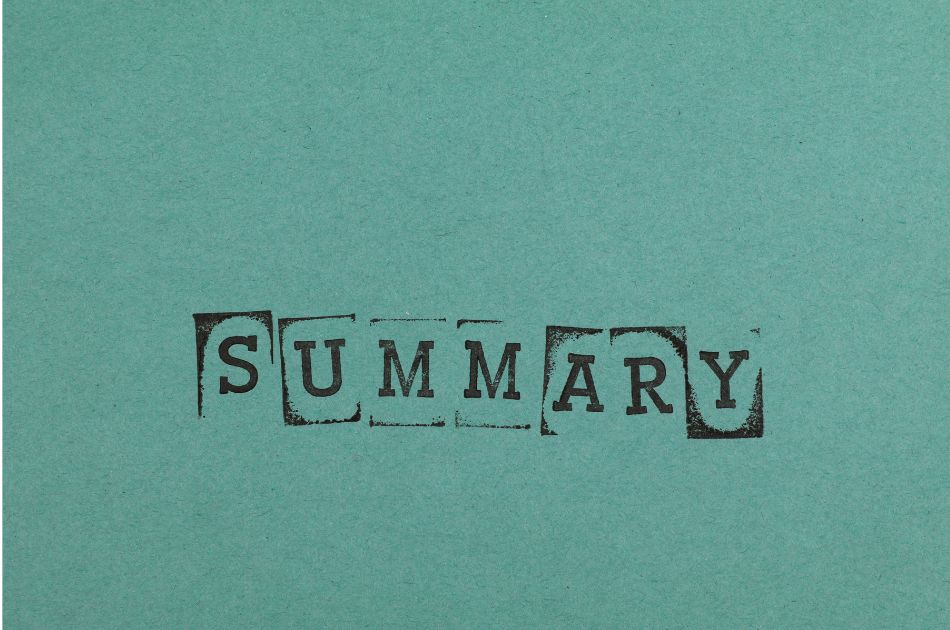
今回は公務員のボーナスの支給額や計算方法、気を付けるべきことについて解説しました。
退職を考えている方や長期の休暇を取得している方は、ボーナスの基準日を意識することでボーナスが支給される場合があるので、損しないためにも今回の記事を参考にしてください。
「公務員」は本当に「安定」していますか?
- 給料安い【子供を大学進学させれる?】
- 減り続ける退職金【老後は大丈夫?】
- 転職スキルなし【公務員ってスキルある?】
このまま、「副業禁止だから…」って、何もしなければ「不幸」な老後しか見えません。
早く動き出さないと、時代から取り残されてしまいます。
>>【2023年最新】公務員バレてもOK!副業7選【合法裏ワザ】
>>「今だけ」無料の投資講座を受ける
>>副業バレをビビっている公務員はコレがおすすめ!
結論、以下の3つを守ればバレません。
- 家族以外に話さない
- 住民税の納付に注意
- 勤務中にしない
それでも、心配であれば以下の2つの方法を紹介します。
- バレてもいい副業をする
>>公務員バレてもOK!おすすめ副業7選 - 家族名義で副業をする
>>公務員が副業するなら家族名義が最強



