
今年の冬のボーナスはいくらもらえるかな?人事院勧告でもう決まっているよね?
年末になると、今年の冬のボーナスはいくらもらえるかと不安と期待でいっぱいですよね。
しかし、ボーナスの額や支給日は、公務員と民間企業で異なる点が多々あります。特に、公務員のボーナスは、人事院の勧告に基づいて決まります。
2023年度の人事院勧告では、「公務員の給与とボーナスがともに引き上げられる」ということで発表されました。
この記事では、2023年度の人事院勧告の内容と、公務員の冬のボーナスの支給日や平均支給額について詳しく解説します。
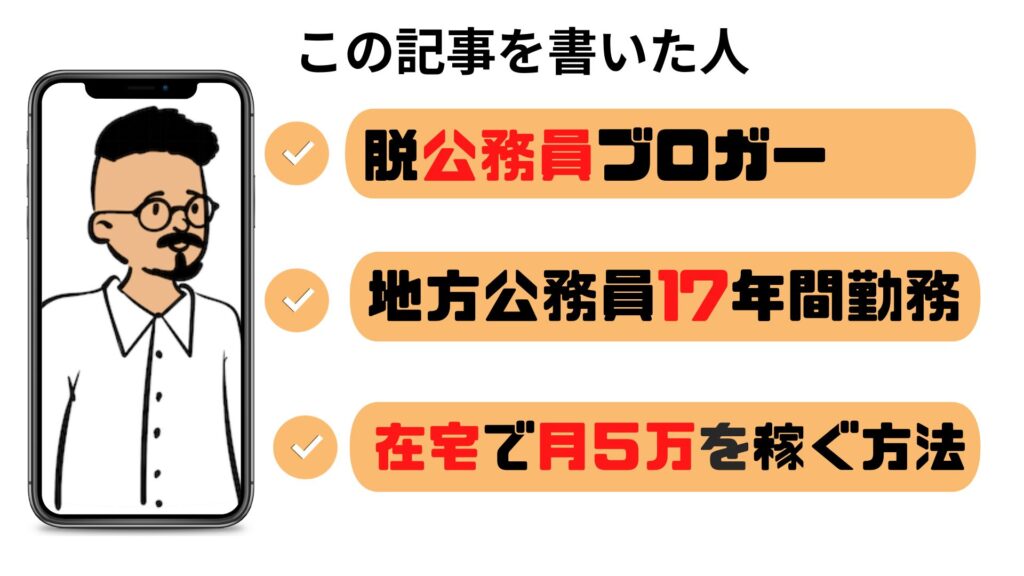
公務員の2023年冬のボーナスは2.30か月分【0.1か月分増額】

2023年度の公務員のボーナスは年間4.40か月分→年間4.50か月分に増額しました。
2023年度の冬のボーナスは、期末手当が1.25か月分、勤勉手当が1.05か月分、合計2.30か月分となります。
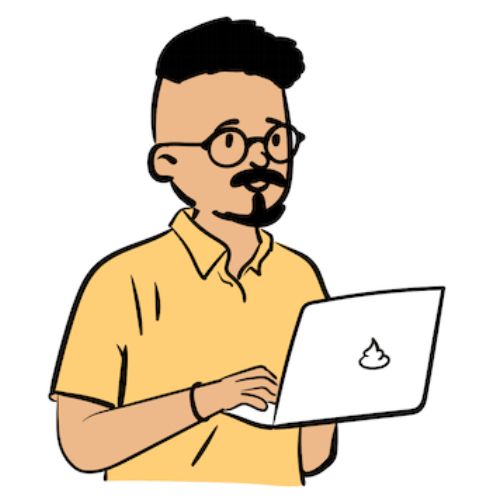
2022年度のボーナスが4.40か月分だったことから、0.10か月分増額されたことになります。
| 令和5年度 | 夏のボーナス | 冬のボーナス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 期末 | 1.20か月 | 1.25か月 | 2.45か月 |
| 勤勉 | 1.00か月 | 1.05か月 | 2.05か月 |
| 合計 | 2.20か月 | 2.30か月 | 4.50か月 |
公務員の2023年度の人事院勧告の背景と内容

2023年の公務員の冬のボーナスは、人事院が2023年8月に発表した人事院勧告に基づいて支給されます。人事院勧告では、公務員の給与やボーナスの基準や支給額を決めるために、民間の給与水準との比較や、公務員の人材確保やモチベーションの向上などの観点から、以下のような内容が示されました。
公務員の月例給の見直し
2023年度の人事院勧告では、公務員の月例給を平均3,869円(0.96%)引き上げることを勧告しました。これは、1994年度以来29年ぶりに4,000円を超える上げ幅となりました。 また、過去5年間の官民較差平均約360円と比べて、約10倍の上げ幅となりました。
月例給の改定は、初任給や若年層に重点を置いて行われました。初任給は、大卒程度が11,000円、高卒程度が12,000円引き上げられました。これは、33年ぶりに1万円を超える上げ幅となりました。行政職俸給では、1級が5.2%、2級が2.8%、3級が1.0%、4級が0.4%、5級以上が0.3%引き上げられました。
月例給の改定は、2023年4月から遡って適用され、2023年12月末にまとめて支給されます。月例給が上がると、それを計算根拠とする各種手当やボーナスも上がります。また、今年度の退職者にも遡って適用されます。
公務員の初任給の見直し
2023年の人事院勧告では、大卒と高卒の初任給を33年ぶりにともに1万円超増やすことを勧告しました。

これは、公務員の人材確保やモチベーションの向上を図るための措置とされています。
これは、2022年度の初任給と比べて、大卒で1万1,000円、高卒で1万2,000円の増額となります。また、1990年度以来、33年ぶりに大卒・高卒ともに1万円を超える上げ幅となります。
公務員の在宅勤務等手当の新設
在宅勤務等手当とは、国家公務員のテレワークで発生する自宅の光熱費や水道代などの相当分を補助するために、人事院が新設することを勧告した手当です。
在宅勤務等手当の新設の背景と目的は、以下のとおりです。
- コロナ禍で在宅勤務(テレワーク)が普及したが、現行の給与体系では、在宅勤務で生じる負担に対応していなかった。
- 在宅勤務で自宅の光熱費や水道代などが増加することは、社員にとって不公平感や不満を生む可能性があった。
- 在宅勤務等手当を支給することで、社員の負担を軽減し、柔軟な働き方を推進することができる。
在宅勤務等手当の新設の内容と実施時期は、以下のとおりです。
- 住居その他これに準ずる場所で、一定期間以上継続して1箇月当たり10日を超えて正規の勤務時間の全部を勤務することを命ぜられた職員に支給する。
- 手当額は月額3,000円とする。
- 令和6年4月1日から実施する。
- 在宅勤務等手当の新設に伴い、通勤手当の取扱いを見直す。
公務員の選択的週休3日制の導入
選択的週休3日制とは、国家公務員が希望する場合に、週に3日の休日を取得できるようにする制度です。この制度は、2023年8月に人事院が国会と内閣に提案したもので、2025年4月から実施される予定です。
選択的週休3日制の導入の目的とメリットは、以下のとおりです。
- 公務員のワーク・ライフ・バランスの向上。週休3日制により、公務員は育児や介護、学習やボランティア、副業や複業など、自分のライフスタイルに合わせた働き方や生き方ができるようになります。
- 公務人材の確保と活用。週休3日制により、公務員の仕事へのやりがいやモチベーションが高まり、生産性や創造性が向上します。また、公務員の職場の魅力が高まり、優秀な人材の採用や定着が促進されます。
選択的週休3日制の導入の方法と条件は、以下のとおりです。
- フレックスタイム制の活用。週休3日制を選択する公務員は、フレックスタイム制を利用して、勤務時間の総量を維持した上で、週に1日を限度に勤務時間を割り振らない日(ゼロ割振り日)を設定します。
- 公務の運営に支障がない限り。週休3日制を選択する公務員は、公務の運営に支障がないと認められる場合に限り、勤務時間の割り振りを変更することができます。
- 勤務時間管理システムの改修。週休3日制を選択する公務員の勤務時間の割り振りや変更を管理するために、勤務時間管理システムの改修が必要です。
以上が、人事院勧告の「選択的週休3日制の導入」についての説明です
公務員の2023年度の冬のボーナス支給日は?【12月8日】

2023年度の公務員のボーナスの支給日は、通常は12月10日ですが、2023年の12月10日は日曜日であるため、12月8日(金)に支給されることとなります。支給日は、法律によって決められています。法律では、支給日は「毎月10日」と定められていますが、10日が土曜日や日曜日や祝日の場合は、その前の平日に支給されます。
公務員の冬のボーナスのおすすめの使い方

公務員(国、地方)の1人当たりのボーナスは平均で約70万円程度と言われています。
このお金をどう使うかは、個人の自由ですが、将来のために投資をすることをおすすめします。なぜなら、投資をすることで、お金を増やすチャンスがあるからです。
投資と言っても、色々な方法があります。例えば、株式や債券、不動産、仮想通貨などです。これらの投資は、それぞれにメリットとデメリットがあります。メリットは、高い利回りや資産価値の上昇などです。デメリットは、価格の変動や手数料、リスクなどです。投資をするときは、自分の目的や期間、リスク許容度などを考えて、適切な投資商品を選ぶ必要があります。
まとめ
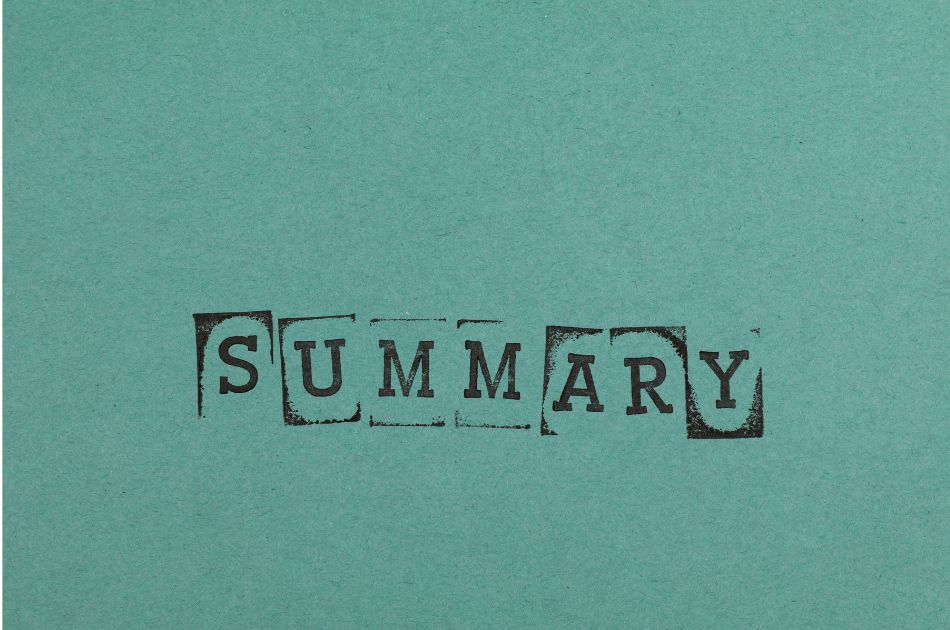
公務員の冬のボーナスは、2023年度の人事院勧告により、2.30か月分という支給額が決定しました。これは、公務員の給与水準が民間企業に比べて低下しているという課題に対応するための措置です。
「公務員」は本当に「安定」していますか?
- 給料安い【子供を大学進学させれる?】
- 減り続ける退職金【老後は大丈夫?】
- 転職スキルなし【公務員ってスキルある?】
このまま、「副業禁止だから…」って、何もしなければ「不幸」な老後しか見えません。
早く動き出さないと、時代から取り残されてしまいます。
>>【2023年最新】公務員バレてもOK!副業7選【合法裏ワザ】
>>「今だけ」無料の投資講座を受ける
>>副業バレをビビっている公務員はコレがおすすめ!




