
公務員を辞めようかと思っているんだけど、どういう手順で辞めたらいいのかな?
公務員としての円満な退職を実現するためには、慎重な計画と適切な手続きが欠かせません。
本記事では、公務員の方々が円滑かつ円満な退職を迎えるために知っておくべきステップを詳しく解説します。
公務員特有の規定や手続き、さらには退職後のお金の面についても触れながら、円満退職のための具体的な手順をご紹介します。
退職を考えている方や将来の準備を進めている方々にとって、有益な情報となることでしょう。
- 公務員と民間企業の違い
- 公務員の退職の流れ・手順
- 公務員退職までの準備
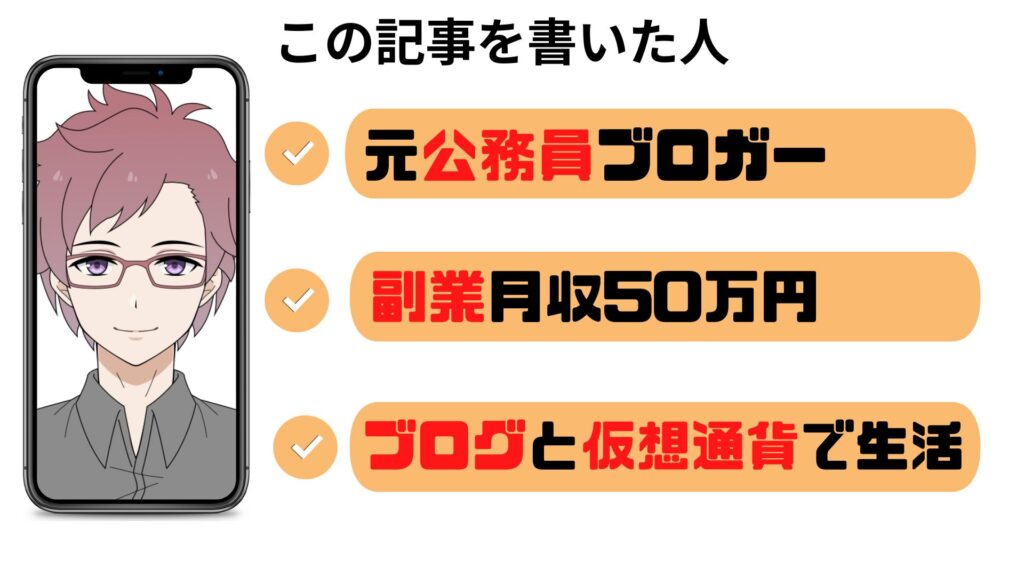
結論、以下の3つを守ればバレません。
- 家族以外に話さない
- 住民税の納付に注意
- 勤務中にしない
それでも、心配であれば以下の2つの方法を紹介します。
- バレてもいい副業をする
>>公務員バレてもOK!おすすめ副業7選 - 家族名義で副業をする
>>公務員が副業するなら家族名義が最強
公務員と民間企業の退職方法の違い
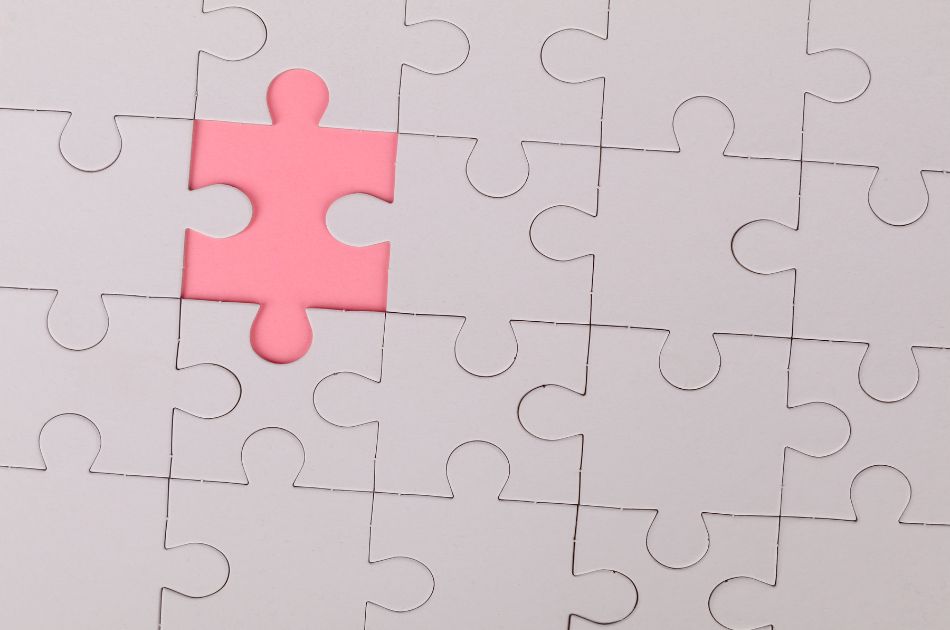
公務員と民間企業では、退職に関するルールや手続きにおいて様々な違いがあります。
公務員の方が円満な退職を目指す際には、民間企業とは異なるポイントを把握しておくことが大切です。
ここでは、公務員と民間企業の退職方法における重要な違いについて以下の4つを解説します。
- 退職の規定の違いに注意
- 辞令の交付が必要
- 公務員の出社拒否やバックレは危険
- 自衛隊の退職は特に困難
退職の規定の違いに注意
公務員と民間企業の退職における規定には重要な違いがあります。
民間企業の場合、雇用期間に定めがない場合でも、社員はいつでも退職の申し出が可能です。例え会社が同意しなくても、退職の意思を申し出た日から14日が経過すると、会社を辞めることができると民法第627条で規定されています。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法

公務員も期日があるのかな?
公務員の場合は「具体的な期日」の定めはありません。
国家公務員の人事院規則では
人事院規則第51条(辞職)
任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
引用元:人事院規則
地方公務員法にも、具体的な期日に関する文言はありません。
各自治体の服務規程などに「退職希望日の何日前までに退職願を出せばいいのか」が書いてあるので、確認しておきましょう。

…とはいえ、退職金の計算もありますし、退職の申し出は早いに越したことはないですね。
辞令の交付が必要
公務員が退職する際には、辞令の交付手続きが必要です。
しかし、退職に伴う式典や儀式に参加したくないという方もいますので、辞令交付式は欠席できます。
欠席を希望する場合、後日郵送で辞令を受け取ることも可能です。また、辞令を受け取るためには、職場に直接取りに行くこともできます。
公務員の出社拒否やバックレは危険
「今すぐにでも辞めたい」という気持ちに駆られても、無断欠勤は避けましょう。
公務員が無断欠勤をすると、懲戒処分の対象となります。したがって、出社拒否やバックレることは大変危険です。
公務員が無断欠勤をすると懲戒処分の対象となってしまうため、出社拒否やバックレるのは危険です。
公務員の場合、欠勤に関しては人事院の懲戒処分の指針によって規定されています
懲戒処分の指針【欠勤】
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
引用元:人事院「懲戒処分の指針について」
民間企業とは異なり、公務員にとって「無断欠勤」は大きなリスクを伴います。
仕事に行くのが辛くても、可能な限り有給申請を行うなど、適切な手続きを取ることを心掛けましょう。
メディア掲載実績多数!【退職代行ガーディアン】有給休暇は労働者に認められた権利ですので、公務員でも有給休暇を使用して、そのまま退職も可能です。退職辞令を受け取るまでの期間を有給休暇として取得する人が多いですね。
自衛隊の退職は特に困難
公務員の中でも自衛隊は、市役所職員や教員とは異なる特殊な規定が存在します。
自衛隊法第40条には「自衛隊の任務を遂行するため最小限度必要とされる期間、その退職を承認しないことができる」と明記されています。
そのため、自衛隊に所属している場合、退職を申し出ても断られる可能性があります。ただし、特別な事情がある場合を除いては、退職が認められると定められています。
自衛隊法第40条(退職の承認)
第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
引用元:自衛隊法

大災害があって、災害派遣されていたりしたら、さすがに退職を認められないよね。
公務員の円満退職までの流れ

ここからは、退職までの流れを具体的に解説します。
- 3ヶ月前退職の意思を伝える
- 2ヶ月前退職願を提出
- 1ヶ月前業務の引継ぎ、退職関係書類の提出
- 1週間前挨拶まわり
公務員の退職には時間と順序が重要です。
民間企業とは異なり、公務員は通常「中途採用」を行っていません。そのため、年度途中での退職は所属部署にとって1名の欠員となります。
円満な退職を実現するためには、退職時期を考慮することが重要です。できる限り年度末に退職することが理想的です。年度末であれば、組織にとっての業務の切り替えや人事調整がしやすくなります。

「転職活動」とも調整しなければいけませんね。
上司への退職の報告
退職を決意したら、上司への報告が最初の重要なステップとなります。
退職の報告は突然やるべきではありません。

報告して、了承されたら、あとは事務的な作業ですね。
事前に上司との面談の予約を取り、時間を設けてゆっくりと伝えることが望ましいです。また、報告の際には以下の内容に注意してください。
- 退職意思を伝える相手
- 伝える内容
- 退職を伝える時期
- 退職理由は「ポジティブ」に
退職意思を伝える相手
第一に伝えるべき相手は「直属の上司」です。
報告する順序を守ることはマナー遵守の一環です。直属の上司を飛び越えて課長や部長に直接伝えることは避けましょう。
まずは直属の上司に対して口頭で「お話したいことがあるので、お時間をいただけないでしょうか?」と丁寧にアポイントメントを取りましょう。
伝える内容
何も考えていかないと、「退職引き留め」にされるので、以下の点をしっかりと整理して報告してください。
- 退職の意思
明確に「退職したい」という意志を伝えます。自信を持って意思を述べることが大切です。 - 退職希望日
可能な限りの有給休暇の消化もお願いしましょう。 - 感謝と挨拶
上司や同僚、職場での経験やサポートに感謝の意を伝えましょう。
退職を伝える時期
退職の意思を伝える時期としては、一般的には退職の約3ヶ月前を目安とします。早めに報告することで、職場や上司に十分な時間を与えることができます。

公務員特有ですが、年度の途中で退職することは結構大変です。
退職理由は「ポジティブ」に
退職理由を伝える際には、「ネガティブ」な要素や批判的な内容は避けるべきです。なぜなら、そういった理由を伝えると上司や職場が改善策を提案し、引き留められる可能性があるからです。
一方で「ポジティブ」な退職理由であれば、上司は応援するしか選択肢がありません。
「新しい分野にチャレンジしたい」「こういったキャリアを積みたい」と前向きな理由を伝えてください。
退職願を提出
退職が承認された後は、「退職願」などの書類関係の準備が必要となります。
退職の手続きと並行して進める必要があるのが共済組合関連の手続きです。以下の項目について担当者からの説明に従い、手続きを進めましょう。
- 共済組合貯金の解約手続き
- 共済組合員証の返納手続き
- 各種保険の解約手続き
これらの手続きに関しては、不安を感じるかもしれませんが、総務担当や人事担当職員から丁寧な説明がありますので、指示に従って進めることが大切です。受け身で手続きを進めることが基本です。
業務の引き継ぎと有給休暇
ここまできたら、難しいことはありません。
業務の引継ぎ
業務の引き継ぎは、後任の職員がスムーズに仕事を引き継げるように行われます。
引き継ぎの際には、上司とも確認しながら進めることが大切です。退職予定が年度末であれば、2月中には引き継ぎを完了させることを目指しましょう。
有給休暇の消化
有給休暇は労働者に与えられた権利ですので、積極的に取得しましょう。

公務員であれば、有給休暇は1年で20日付与され、最大40日までに繰り越すことができますね。
同僚や職場に迷惑をかけることを気にするかもしれませんが、新たなスタートを切るためにも有給休暇を充分に利用することをおすすめします。
挨拶まわり
退職日の1週間前くらいから、挨拶まわりを行うことが一般的です。
特に地方公務員の場合、同じ地域に住んでいる方々と今後も顔を合わせる機会があるため、丁寧な挨拶は重要です。
退職理由や転職先の詳細を伝えない方が、変な噂が広まる可能性を減らすことができます。
公務員退職後のお金

公務員を退職した後の経済面について考えてみましょう。
公務員を退職後、1年間くらいは失業手当をもらって生活しようと思っている方もいるかもしれません。
しかし、公務員の方に残念なお知らせです。
国家公務員や地方公務員は、失業のリスクが少ないため雇用保険法第六条で雇用保険の対象外となっており、失業保険は受け取れません。
それに相当するものとして、退職手当の受給は可能です。
公務員は失業手当をもらえない
公務員は一般的な会社員と異なり、雇用保険法の適用対象外となっているため、退職後に失業手当を受け取ることはできません。
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
引用元:雇用保険法 第6条 適用除外
公務員は通常、安定した雇用形態で働くことが多く、失業のリスクが低いとされています。そのため、雇用保険の制度は公務員には適用されていません。
ただし、退職時に支給された「退職金」の額が、雇用保険の失業手当に相当する額に満たず、かつ退職後一定の期間失業している場合には、その差額分が失業者の退職金として支給されます。
また、公務員の中でも日本郵政株式会社や国立大学法人など、雇用保険法の適用事務所に勤務していた場合は、退職後に雇用保険の申請を行うことで失業保険を受け取ることが可能です。
公務員の退職金
公務員は退職後に失業保険を受け取ることはできませんが、代わりに退職金が支給されます。
国家公務員や地方公務員には退職手当制度があり、一定の支給要件を満たすことで退職時に退職金を受け取ることができます。
退職金の額は、勤続年数や給与水準などに基づいて算定されます。
国民年金
国民は、すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中も国民年金への加入が必要です。
退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区役所または町村役場で手続きを行う必要があります。この手続きにより、国民年金の加入が確認されます。
まとめ
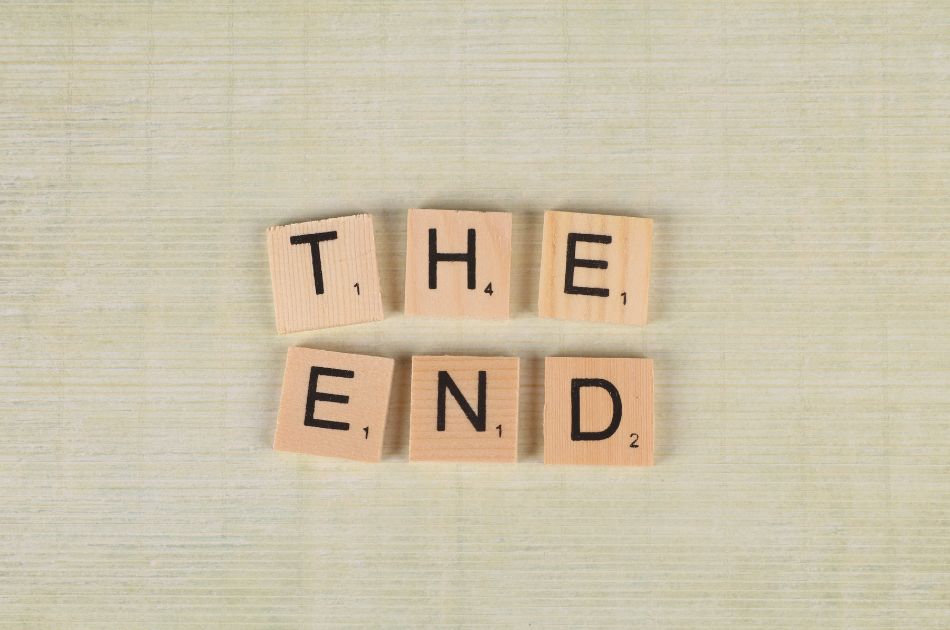
今回は、公務員の退職手順を解説しました。
円満な退職を行うことで、新しいスタートを切ることができます。
以下の手順を確認しておきましょう。
- 3ヶ月前退職の意思を伝える
- 2ヶ月前退職願を提出
- 1ヶ月前業務の引継ぎ、退職関係書類の提出
- 1週間前挨拶まわり
公務員を辞める選択も続ける選択も勇気のいる決断です。
自分の人生に後悔のないよう、将来の幸福と成長を追求する道を選びましょう。新たなステージでの成功を祈っています。
結論、以下の3つを守ればバレません。
- 家族以外に話さない
- 住民税の納付に注意
- 勤務中にしない
それでも、心配であれば以下の2つの方法を紹介します。
- バレてもいい副業をする
>>公務員バレてもOK!おすすめ副業7選 - 家族名義で副業をする
>>公務員が副業するなら家族名義が最強




